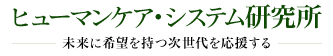老朽住宅改修 第33回 外壁・外構工事も終わる~近所では 何をやっているかと噂になっていたと知る
2025年3月26日

1月末に解体した外壁・外構もやっと9月後半に工事終了。
檀那寺の住職から、近所では「何をやっているのか・・」 と噂になっていたことを聞きました。
10月の母の誕生日に、檀那寺の住職に、慰霊の場として完了した仏間で、お経をあげてもらった時の話です。確かに、近所の人は外観しか見えず、内部でやっていることは見えませんので、不思議に思っていただろうと、その時、初めて気づきました。
1月末に木造部の東側にある築70年前後(推定)のブロック塀を撤去し、家屋の周囲を足場とブルーシートで囲って外壁も撤去~耐震工事終了後の4月に外壁を復旧してブルーシートも撤去しました。しかし、東側の介護室の窓周囲、西側のサンルームの周囲は、その後の工事の対象のため新たな外壁設置は先送り・・足場もブルーシートも一部残りました。それぞれ6月までには窓等が設置され、ブルーシートは撤去されましたが、外壁業者の日程が合わず・・下地がむき出し=道路からは工事中断のように見える状態が、木造部の外壁工事が完了する8月半ばまで続きます。
さらに鉄骨部の外壁工事が始まったのは、トイレの窓をつぶす措置が完了した9月半ばでしたので、それぞれ数ヶ月の間を開けて都合3回の外壁工事があったことになります。
これを書いていて、昔中国で多数見た「資金が無くて工事中に放置されたビル」を思い出しましたが、近所の人も同じ思いだったに違いありません。
塀の復旧は、解体後8か月間放置されからの完了ですので、その間の長さは普通ではないと思うのが通常でしょう。単に、外壁と塀の間が狭く、外壁が終わらないと工事着手できないということなのですが、事情が分からないと、「なぜ壊して直ぐに作らない」と考えるでしょう。たぶん私もその一人です。
当初、塀の更新実施はその他の検討事項の一つでしかなかった=今回やる必要もないかと考えていた事項ですが、能登半島地震で考えが変わり、子供が通る頻度の高い東側の通りに面する老朽ブロック塀は撤去することにしたものの・・関心の高い工事ではなかったので、8月後半に入って初めて、いつやるのかと気になった程度です。
その復旧は、土台となるブロックを2段だけ新たに積んで、目隠しで最低必要な高さまで軽量のフェンスを立てる=計2日で終わりです。家だけでなく、外構でも耐震措置というところでしょうか。補助制度もあると聞き調べましたが、福井の制度では、手続に要する手間のほうが高そうだったので諦めました。
また、その塀に続く、築50年程度のブロック塀は、庭の土留めの役割もあることから撤去・更新はあきらめて、土留めの役割に必要な部分は残して、不要な上部は切り落とし・・約半分の高さ(写真)になりました。
その結果、通りから庭の状況がよく見えるようになったことに気づいた奥方は、直ぐに春に花の咲く球根をホームセンターで購入し、道路側から「土留め」際に植え込みました。今年の春には、○○が咲く予定です。塀の撤去等は安全確保のほかに、庭などの敷地の有効利用につながる面があることを知りました。
ちなみに費用は、耐震補強時の外壁工事も含めて、外壁・外構で約2万円/㎡(床面積)でした。外壁材が、当時、急激に上昇したらしく、当初予定以上に費用が増えた要因の一つだったようです。
それから、工事が停滞しているように見えると気づいたら、ご近所に雑談交えての事情説明も忘れずに・・。