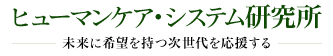Episode52 「組織はあてにならない 最後は自分」
2013年6月8日

私は、厚生労働省保険局を3回経験しています。それも外国での3年間の勤務を挟んでの10年の間にです。Ⅰ種採用と言われたグループで、3回も同じ局に行けば、審議官等の指定職になるものですが、私の3回目の保険局は、企画官としてでした。
さすがに、保険局への異動の内示をもらったときには、納得がいかず、直接人事課長にその理由を聞きに行きましたが、「患者負担が3割となった法律改正の際に、今後の新たな医療保険制度を明確にすることが義務付けられたが、それを考える『即戦力』だ。」と、理由にならない理由を言われ・・。文句を言っても人事が変わることはないので、気を取り直して保険局総務課に着任。高齢者医療制度等の新たな枠組みの議論を始めました。
さすがに、保険局への異動の内示をもらったときには、納得がいかず、直接人事課長にその理由を聞きに行きましたが、「患者負担が3割となった法律改正の際に、今後の新たな医療保険制度を明確にすることが義務付けられたが、それを考える『即戦力』だ。」と、理由にならない理由を言われ・・。文句を言っても人事が変わることはないので、気を取り直して保険局総務課に着任。高齢者医療制度等の新たな枠組みの議論を始めました。
それから、数か月後、またも人事課長から「即戦力」と言われることとなりました。北朝鮮拉致被害者の5名が帰国するに際して、国内支援班の責任者に指名された時です。
5名の帰国の前提として、小泉総理(当時)と金主席(当時)のトップ会談が行われ、何名かが一時帰国するとの報道がなされたときは、私は、もちろん自分が関わることなど、想像もせず、新しい高齢者医療制度をどう世の中に問うかを若手補佐等と検討していましたが、数日後、保険局長から呼ばれ、いつもとは違う不機嫌な顔で、「絨毯部屋の○○さんの所に行ってくれ」と言われ、その部屋に出頭すると、「本日、午後から重要な会議があるので行ってくれ」との由。これが拉致被害者帰国支援の始まりでした。
会議に参加して帰国支援の話と初めてわかり、戻ってきて理由を確認しに人事課長に行ったときに、「中国経験」「福井県出身(地村夫妻)」と理由にならないことを言われ、加えて「即戦力」と・・厚生(労働)省の当時の人事当局の「即戦力」の安売りにあきれたものです。
5名の帰国の前提として、小泉総理(当時)と金主席(当時)のトップ会談が行われ、何名かが一時帰国するとの報道がなされたときは、私は、もちろん自分が関わることなど、想像もせず、新しい高齢者医療制度をどう世の中に問うかを若手補佐等と検討していましたが、数日後、保険局長から呼ばれ、いつもとは違う不機嫌な顔で、「絨毯部屋の○○さんの所に行ってくれ」と言われ、その部屋に出頭すると、「本日、午後から重要な会議があるので行ってくれ」との由。これが拉致被害者帰国支援の始まりでした。
会議に参加して帰国支援の話と初めてわかり、戻ってきて理由を確認しに人事課長に行ったときに、「中国経験」「福井県出身(地村夫妻)」と理由にならないことを言われ、加えて「即戦力」と・・厚生(労働)省の当時の人事当局の「即戦力」の安売りにあきれたものです。
さらに、絨毯部屋の住人からは、「地元へは外務省が行く。君らは地元に行く必要はない。」「東京で連絡調整をするだけで、1週間と聞いている。」と言われましたが、実際には「外務省がリエゾンにつくが、厚労省で万全の態勢をとる」「いつまで拉致被害者が日本にいるかは未定」と、今回の帰国支援の責任者から伝えられ・・話が違うと、再度、絨毯部屋に確認に行くと、今度は、「君に任せる」と言うだけで何ら指示もありませんでした。
もう言っても無駄と考え、帰国支援のロジ室となった赤坂プリンスホテル(当時)に行くと、総勢100人近い規模の人員を投入する軍隊並みの外務省に対し、私を含めてたった3名の厚生労働省の竹槍部隊との違いを見て、さらに溜息です。
もう言っても無駄と考え、帰国支援のロジ室となった赤坂プリンスホテル(当時)に行くと、総勢100人近い規模の人員を投入する軍隊並みの外務省に対し、私を含めてたった3名の厚生労働省の竹槍部隊との違いを見て、さらに溜息です。
最終的には、「地元に行くは必要ない」との厚労省幹部の指示を無視して、3人で相談し、「地元に先乗りして受入自治体の支援を行い、長期的にも対応できるようにしよう。」と方針を決めました。しかし、3人とも地元に行くと、東京での支援体制がなくなるので、最も受入れがしっかりしていると見た福井については、厚生労働省ではなく外務省の力を借りることにし、私から直接外務省の責任者に依頼をしました。帰国者がホテルで記者会見をした翌日に、厚生労働省に報告することもなく(しても時間の無駄という判断)、そのまま各地元に移動。私が行ったのは、地元も家族の力も最も弱いと見た佐渡でした。
それからの1週間は、例えれば台風の中で土嚢を積む現場監督のような仕事でした。
終了後、特に、絨毯部屋や人事課に報告することもなく、保険局の仕事に戻りましたが、特段の問い合わせもありませんでした。組織としては、うまくいって当たり前とのことなのでしょうが、個人から見れば、組織はあてにならないと実感した一件となりました。
それからの1週間は、例えれば台風の中で土嚢を積む現場監督のような仕事でした。
終了後、特に、絨毯部屋や人事課に報告することもなく、保険局の仕事に戻りましたが、特段の問い合わせもありませんでした。組織としては、うまくいって当たり前とのことなのでしょうが、個人から見れば、組織はあてにならないと実感した一件となりました。
なお、今でも、曽我さん親子が対面した際に演じられた幽玄な鬼太鼓(おんでこ)(写真)は、あの嵐のような仕事とともに、忘れられない記憶となっています。
いずれ落ち着いたら、また見に行きたいと思いつつ、既に12年を経過しました。
いずれ落ち着いたら、また見に行きたいと思いつつ、既に12年を経過しました。